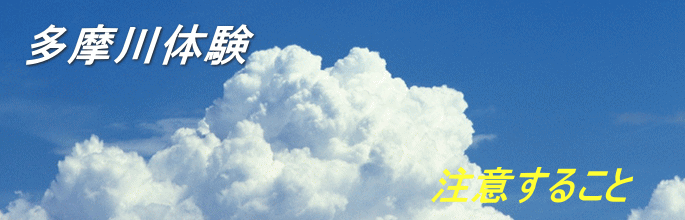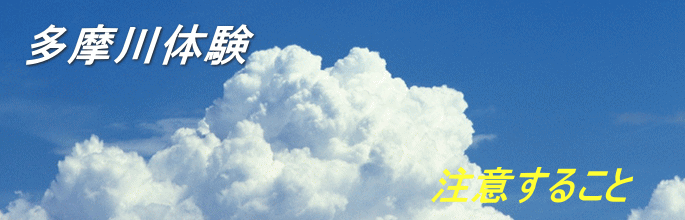|
《タマゾンガワ》
まず、多摩川流域にある下水処理場を調べました。
(〇は多摩川に直接処理水を排水しているところ。)
〇多摩川上流水再生センター 青梅市・昭島市・福生市・羽村市・瑞穂町の大部分と立川市・武蔵村山市・奥多摩町の一部
〇南多摩水再生センター 多摩市・稲城市の大部分、八王子市・町田市・日野市の一部
〇北多摩一号水再生センター 府中市・国分寺市の大部分、立川市・小金井市・小平市・東村山市の一部
〇等々力水処理センター 中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区にわたる多摩川右岸 →一部 江川せせらぎ スラッジセンター
・入江崎水処理センター 川崎区の全域と幸区・中原区の一部 →東京湾
・加瀬水処理センター 多摩川と矢上川・鶴見川にはさまれた・幸区、中原区、高津区・宮前区の一部 → 鶴見川支流、矢上川
・麻生水処理センター 麻生区の大部分 → 鶴見川支流、麻生川
|

(夢見ヶ崎動物公園のカミツキガメ)

(外来種ではない) |