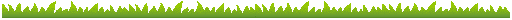
等々力緑地で見られる野鳥たち
現在、飼育目的で日本国内にいる野鳥を捕獲することは原則禁止されております。○今回見られた野鳥 ×残念ながら見れなかった、季節的にいない野鳥
| 今までの野鳥観察で見かけた鳥たちです。フィールドノートに等々力緑地の地図が入っているのでどこで見かけたか番号を書いておこう!! |
| 番号 | 図 | 名前 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 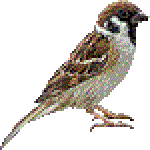 |
スズメ | 都会鳥・・・最近はスズメを採ることもなくなりました。 私たちが一番見ることの多い野鳥。人家のそばに住む鳥で、森の奥深い所にはいないという小鳥です、昔から人間とは深いかかわりをもっている鳥ですが人に馴れるわけではありませんが最近は人から餌をもらうちゃっかりものもいるようです。 スズメをバカにしてはいけませんバードウオッチングはこの鳥から始めるのが基本だそうです。 |
〇 |
| 2 |  |
ノスリ | カラスと一緒にいることも多いタカ科の鳥 平地から山林に生息する。冬期は低地の農耕地や川原、市街地の公園などでも見ることができる。 ピーエーという鳴き声に特徴がある。 |
|
| 3 |  |
トビ(トンビ) | トンビがヒュルリと輪を描いた・・・。 タカ科の中では比較的大型であり、全長は60〜65cmほどで、カラスより一回り大きい。 上昇気流に乗って輪を描きながら空へ舞い上がる様や、「ピーヒョロロロ、ピーヒョロロロ」という鳴き声はよく知られています。日本ではもっとも身近な猛禽類です。 カラスとは犬猿の仲といわれるほど、カラスに集団で追い回されているのをよく見かけます。 |
|
| 4 |  |
チョウゲンボウ | ハヤブサ科に属する小型の猛禽類。 農耕地、原野、川原、干拓地、丘陵地帯、山林など低地帯から高山帯までの広い範囲に生息する。「キィキィキィキィ」と聞こえる声で鳴く。 ネズミや小型の鳥類、昆虫、ミミズ、カエルなどを捕食する。素早く羽ばたいて、斜めになりながらホバリングを行った後に急降下して地上で獲物を捕らえることが多いのが特徴。 多摩川ではよくスズメを捕食しているところを見ることができる。 |
|
| 5 |  |
ハシブトカラス | 都会のカラス 皆さんの家の近くでよく見るカラスでくちばしが太く、額が出っ張っていて「カアカア」と鳴くのが特徴。 つがい(オス・メス)でいることが多く、生涯ともにするようです。 夫婦仲が良く、子育て熱心で知られており、皆さんのなかにはカラスにおそわれた経験があるかと思いますが子育て中によくおきることで、カラスの巣があるところには近づかないようにしましょう。 また、地表を歩くときは両足をそろえてピョンピョンはねて移動します。 タカの仲間が嫌いで縄張りに入ってくると集団で鳴きながら追い回します。 |
|
| 6 | ハシボソカラス | 田舎のカラス 郊外とか畑や河川敷などで多く見られるカラスで、大きさはハシブトカラスより少し小さめで、くちばしは細く、額はなだらかでおじぎをするように首を上下させて「ガアガア」と鳴くのが特徴。 習性はハシブトカラスと似ているが、ひじょうに頭がよく、堅い木の実を車の通るところに置いておき割ってもらったものを食したりする。 地表に落ちているものを歩いて探す習性があり、足は交互に動かして歩きます。 |
〇 |
|
| 7 |  |
オナガ | カラスの仲間 鳴き声がうるさい。グェーイ・グェーイと聴こえる。今は本州以北でしか見れなくなり留鳥として民家のそばでも見ることができる。関西の人達には貴重な鳥として人気がある。 |
〇 |
| 8 |  |
モズ | モズのハヤニエ 頭が大きく尾も長めで頭は橙褐色、キュン・キュンとかキーィキイキイなどの高鳴きをする。 捕えた獲物を小枝やとげにさす習性を「モズのハヤニエ」という。 後で食するためであるが、その場所を忘れてしまい他の鳥に食べられてしまうなど、忘れん坊の人にたとえられることもある。 |
〇 |
| 9 | ヒヨドリ | 街の騒音屋 大きさはハトより少し小さめな鳥、等々力緑地で一番見かける野鳥。「ピィーヨ、ピーヨ」と騒がしいくらいに大きな鳴き声で飛びまわり、(波形のような飛び方をします)庭木の枝先などに止まることも多い鳥でよく見かけます。 ナンテンなどの庭木の実が大好物で、冬になると椿やサザンカなどの花の蜜を吸いにやってくることもあります。 ツガイでいることも多く、1羽が庭の木の実などを食べているときはもう1羽は見張りをしています。写真をクリックすると大き目の写真が見れます。 雨どいにたまった水を飲んでいるところです。 |
〇 |
|
| 10 |  |
ムクドリ | 集団で行動 河川敷のグランド、公園の芝生、ゴルフ場や農耕地などで歩きながら地面にいる虫などを探す姿をよく見かけます。 ツグミぐらいの大きさで、頭は黒く白いほほと首から下は黒褐色になることが多い。人間の暮らす場所に生息する鳥で、何千羽の群れをなして駅前の街路樹に集まり弊害をもたらしていることでも有名な鳥。 軒下や戸袋などの間に巣をつくります以外と気の荒い鳥でカラスなどを集団で追い払います。 |
〇 |
| 11 |  |
シジュウカラ | どこにいるのかわからない・・・ いろいろな場所で見かける鳥で街中でも繁殖し、大きさはスズメぐらいの大きさです。高いところで「ツーピー、ツーピ」とさえずりが聴こえたらこの鳥です。 この冬は我が家の柿の木に残しておいた実を食べに頻繁に見かけました、最初は数羽が柿の取り合いで盛んに喧嘩をしておりましたが残ったつがいが毎日のように来ておりました。スズメやメジロなどと行動をともにすることも多い。 |
〇 |
| 12 |  |
メジロ | 一般には鳥獣保護法により捕獲禁止となっており、飼育も禁じられている。 葉のおいしげった木立の中にいることが多い鳥で大きさはスズメよりも少しちいさく頭から尾まで黄緑色で目が白く縁どられているのが特徴、名前はこれからきたもの。 チョウのように花の蜜が大好物で椿、梅、さくらなどの花弁の底の蜜をなめに集団で来ることも多い。 ウグイスと勘違いしているひとも多い。 |
〇 |
| 13 | ツグミ |
渡り鳥 10月〜11月にかけて渡ってくる鳥で身近な冬鳥として有名。ハトより少し小ぶりで背中や翼が褐色の色をしている。とことこ歩いては立ち止まり、胸をはってあたりをみまわしながら地上の食べ物を探しまわります。 初夏には涼しいところに移動します。去年よりは早く見ることができました。 |
〇 | |
| 14 |  |
カワラヒワ | スズメではない 大きさはスズメぐらいで、低山の林や市街地でよく見かけます。秋冬は群れをつくって川原や農耕地などに生息します。全身がオリーブ色で飛ぶとおなかの黄色い帯が目立ちます。木の実や草の実、昆虫などを食べ鳴き声は「キリリコロロ」と聴こえます。 小笠原諸島にだけすむ仲間「オガサワラカワラヒワ」は絶滅種に指定されております。 |
|
| 15 | ハクセキレイ | 道先案内鳥のよう 都会に進出してきた鳥で公園や駐車場など地表の見えるところにいる白と黒のコントラストのはっきりした鳥で尾を上下に振りながら歩き回ります。 人が近づくと「チチッ、チチッ」と鳴きながら行こうとする方向へ素早く歩いたり地表近くを波をうつような感じで飛びます。まるで道先案内をしているようです。 今年は等々力緑地および多摩川河川敷でよく見かけます。(留鳥) |
〇 | |
| 16 |  |
ウグイス | 春告げ鳥 春告げ鳥として鳴き声(ホーホケキョ)の有名な鳥ですウグイスの谷渡りという少し長めの鳴き声で縄張りを宣言する泣き方も聞こえます。繁殖期以外では「チャッ、チャッ」という鳴き声を発し(地鳴き)、街中のやぶや笹の中に隠れて過ごします。全身茶褐色のじみな色をした鳥で声はすれども姿は見えずということでしょうか。 ウグイス色をした「メジロ」と間違われることも多い鳥です。 |
|
| 17 |  |
キジバト | デェデェ、ポーポ 体は灰色がかった色で翼には褐色のうろこ模様があります。鳴き声は「デデ、ポーポー」と聴こえます。 もともとは山にいたハトで「山鳩」ともいいます。 よく見かける「ドバト」は野鳥の分類にははいらないので(外来種)のせませんでした。 住宅地のそばで見かけることが多くなった。 |
〇 |
| 18 |  |
コサギ | 等々力コロニー 全身の羽毛が白色で、いわゆる白鷺と呼ばれる鳥の一種。足の指が黄色いことと、夏羽では頭に2本の長い冠羽が現れること、背の飾り羽は先が巻き上がる 水田、川辺、海岸などで首を縮めて立っている姿がよく見られる。魚類、カエル、ザリガニなどを捕食する。 |
〇 |
| 19 |  |
ゴイサギ | 夜に飛ぶ鳥 昼は寝て夜に活発に活動する鳥。夜間、飛翔中に「クワッ」とカラスのような大きな声で鳴くことから「ヨガラス(夜烏)」と呼ぶ地方もある。 かってサギのコロニーがあった場所(釣り堀のなかの島)にコロニーを作ってくれることを願っております。(かなりの数のゴイサギをみかけました。幼鳥もいるようです) |
〇 |
| 20 | アオサギ | 成鳥の大きさはダイサギと同じくらいで大形の鳥です。等々力にで見かけたアオサギは幼鳥で全体が灰色がかっています。 写真をクリックすると少し大きめの写真がみれます。一番上にいるのが「ゴイサギ」下にいる白い色のさぎが「コサギ」と「アオサギ」です。 |
〇 | |
| 21 |  |
カワウ | 羽をかわかす水鳥 カラスより大きい大型の鳥で潜水して魚をくわえ水面に浮上してから餌を飲み込む習性があります。長良川の鵜飼は有名ですがあの鵜は海鵜です。 水鳥ですが羽に油分を塗りつけることができないため乾かすために頻繁に羽を拡げる行動が多い。 集団で魚を採ることもあます。大師干潟ではたくさんのカワウをみかけますが「アユ」を大量に食すため、数の適正化を実施しないとアユが絶滅する可能性もある。 |
〇 |
| 22 |  |
カルガモ | 都会の真ん中でも生息する 一年中見られるカモ、平地で巣を作り、雌だけで子育てをします。 それだけ天敵に襲われることが多いため、一度に10〜13個を産卵し生き残りを出そうとするものです。 生まれた子供も親から餌を与えられるのではなく自分で餌をついばみます。生存率は街で見かけるカルガモが多いとされています、人間が守ってくれる機会が多いのも事実ですね。 |
〇 |
| 23 |  |
アイガモ | 野生のマガモとカルガモの雑種? 野生のマガモとそれを改良し食肉用にしたアヒルとの交雑交配種。カルガモとアヒル、マガモとカルガモの交配種もある。基本的には人によってつくられたものは自然界に放鳥しないきまりになっております。 |
|
| 24 |  |
カイツブリ | 一生水面で暮らす鳥 カモ類と似ていますが、カモの仲間ではなく、くちばしがとがっていて頭は小さく首は長めで尾がない。等々力公園の釣り池にいるのは一年中いる鳥で渡り鳥にはならない。生涯水上で暮らし、陸に上がったり空を飛んだりすることはほとんどなく、水中に潜って魚やエビなどを捕まえます。 水の上にプカリ、プカリ浮いている姿をよく見かけます。 |
〇 |
| 25 |  |
オカヨシガモ | 冬に来る渡り鳥 雄の頭は褐色で体は灰黒色、お腹は白い。等々力の釣り池では常連です。 |
〇 |
| 26 |  |
キンクロハジロ | 冬にくる渡り鳥 雄は黒色のツートンカラー、冠羽に黄色い目、全長44cmぐらい。湖沼、河川、湾に飛来(北海道では一部繁殖)雄は冠羽が後頭部に垂れている。 今年は見れませんでした。 |
|
| 27 |  |
カワセミ | 多摩川の人気者 水辺に生息する小鳥で、鮮やかな水色の体色と長いくちばしが特徴で、ヒスイ、青い宝石鳥と呼ばれることもある。 海岸や川、湖、池などの水辺に生息し、公園の池など都市部にもあらわれる。古くは町中でも普通に見られた鳥だったが、生活排水や工場排水で多くの川が汚れたために、都心や町中では見られなくなった。近年、水質改善が進んだ川では、特に多摩川や東京都心部でも再び見られるようになってきている。 |
|
| 28 | コゲラ | コゲラの姿初めて見た!! キツツキの仲間で、街中で生息するスズメぐらいの鳥。「ギーッ」という鳴き声に特徴があり木の幹の中の虫を食べるために穴をあけたりする。またねぐらにできるくらいの穴をあけることもある。 冬場はシジュウカラなどの小鳥の群れに混ざっていることも多い。 以外と人どうりのある所の木に穴が開いていることが多い。等々力公園だからなのか? 写真をクリックすると少し大きな写真が見られます。 |
||
| 29 |  |
コアジサシ | 夏鳥 この時期にはいません 全長は24 cmぐらい、ツグミやヒヨドリと同じくらいの大きさでアジサシよりも小さい 海岸や川などの水辺に生息し、狙いをつけて水にダイビングして魚をとらえる。その様子から鯵刺(あじさし)の名前がつけられたと思われる。 巣は川原、砂浜、埋立地などに集団繁殖地(コロニー)を作って外敵の侵入に備える。地面にくぼみを作って2、3個の卵を産む。卵とヒナはまだらもようで石ころと区別がつきにくくなっている。特にカラスの攻撃に逢うことが多い。初夏から夏にかけて見られる。 |
|
| 30 |  |
ユリカモメ | 冬鳥として飛来。 日本では、冬鳥として飛来する。北海道から南西諸島まで広く渡来し、小型のカモメ類の大半を占める。 海岸、内陸の湖沼や河川に比較的大規模な群を作り生活する。大きな河川では河口から10 km以上も遡る。 化石発掘の宿河原堰でもみかけました。 |
|
| 31 |  |
ショウビタキ | 冬の訪れを教えてくれる鳥 住宅地や公園や河川敷などで見ることができます。 |
|
| 32 | エナガ | 全国で見かける鳥ですが等々力緑地では初めて見ることができました。森林や林に生息し群れをつくる習性が強い。体系は小型で尾が長く一見、だんごにくしをさしているように見える。 写真をクリックすると少し大きめの画像を見ることができます。 |
〇 | |
 トップページへもどる
トップページへもどる





