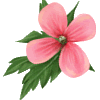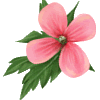
ああ、セレモニー
秋のお彼岸の入りには少し早い、まだ夏の名残を感じる日のことでした。
電車の中で隣に座っていた娘が、
「今日私たち9回目の結婚記念日なの」
「あらまあ、気が付かなかったわ、お墓参りになんて誘って悪かったかな、何かやるの?」
「別に……」
考えてみたら、我が家ほど記念日をおろそかにする家もないようです。
或る午後のことです。夫との会話の中で、
「そういえば今日は何の休日だったかしら?」
「なんだっけ」カレンダーを見て、
「あれ、敬老の日だ」
「へえ、そうだったの、それにしてもみんな知らん顔だねえ」
でもこれは私たちにとって、喜ぶべきことと思うようにしています。
我が家の若いもんたちは、私たちのことを、敬老の日の対象とは認識していないのですから?!
私たちだって自分が年寄りだなんて、さらさら思っていません。
それにしても、おそるべし <sunday ま・い・に・ち>
リタイア生活が身についた昨今は、曜日の観念すらなくなっています。
そして、私たちが祝うべき両親は、もう居ないのですから。
あ、誤解しないで!親が居ないことが喜ぶべきという積りではありませんのよ。
そして、私たち自身結婚記念日なんて、毎年気が付くと過ぎてしまっています。
たまに気が付いて
「今日私たち結婚記念日なのよ」
「へえ、そうなの」
本人同士にして、この現実。
大体我が家のオットセイは、私の話を聞いていません。たとえば……
「お天気いいわね、多摩川にお散歩いかない?」
「……」
「ねえ、聴こえたの?」
「北の湖理事長って、小沢一郎に似てるねぇ」
……って具合です。
ここで私は考えます。こんな人だから、今まで気楽に一緒に居られたんだわ?!
だからお友達が、毎年結婚記念日にホテルへディナーを食べに行く、なんていう話を聞くだけで、まぶしくてクラクラしてしまいます。
でも私は、あるお友達の話を暴露しちゃいます。もう時効だと思うので…
彼女は、毎年の結婚記念日に、結婚式を挙げたホテルで、家族写真を欠かさず撮り続けていました。
(これに関しては、私も見習いたかったのですけれど……)
そして、そのダンディなハズバンドが癌の末期だとわかったとき、その中の一枚の写真を、手回し良く引き伸ばしました。普通の家庭の告別式に使うのより、すくなくとも4倍は大きいサイズです。
何年か経って、彼女の家に行った時見たのは、部屋の隅に立てかけてられていた「ご主人」です。
思わず私が「ああ!」というと、彼女、なんて言ったとおもいます?
「これおき場所がなくて……」
私は何年か前の「その日」にこれを懸念していたのになぁ!勿論返答の仕様がありません。
さて、話を戻しましょう。
夫の誕生日に、思い出してバラの花を彼の部屋に飾ってあげたこともありましたけれど、本人は最後まで気付かず仕舞い!
ある年の彼の誕生日にポロシャツをプレゼントしようと思い立ち、「どんなのが欲しい?」
と聞いたときの答えが振るっています。
「死ぬまでに着きれないほどあるから、イラナイ」
お彼岸の墓参りを、「お盆だからなあ!」といった娘の旦那に至っては、類は友を呼ぶというひと言につきますね。
でももっとうわ手がありました!友人のR子さんの現在100歳にして矍鑠たるお母様とお話していたとき、言われた言葉には完敗しました。
「まあ、あなた、仏様にご飯をおあげになるの?お偉いわねえ、私は生きている人が一番大事なの」
この開き直りそして、この上ない自信!ここに至って私は大拍手を送ります。
人の考え方は、ことほどさように、差があるのですね。
でも、そんな私でさえ、お彼岸になるとそわそわして、お墓参りに行きたくなり、墓前で現在のシアワセをお礼申しあげてくる位の気持はあるんです。
そして、子供たちの誕生日に、プレゼントのことをあれこれ思い巡らすのは、将来のための打算ですのよ。
ふ、ふ、ふ……
この間京都に行った時のことです。足を伸ばして薬師寺にいきましたら、丁度修学旅行の高校生を相手に、若いお坊さんが、説法をしていらっしゃいました。
聞いていたらとてもいい事を言ってらっしゃるのですね。
法相宗の薬師寺は、現世の幸せを願ってくださる宗派で、だからお葬式はしないそうです。
学のない私には、初耳でした。
「みなさん!下を向いている顔ってどういう状態ですか?
これは<面が倒れている>のです。つまり、うつむいていると、何もかもが面倒になる、顔を上げると<面>が白く見えて、これが面白いということなのです。そして、何もかもが面白くなる、だから、いつも顔を上げて暮らしなさい」……と。
女子高生たちの明るい反応も良かったし、若者をひきつける説得力は、流石、かの高田好胤さんの息のかかったお寺!と思いました。
やっぱり、現世の関係を本音で大切にしようとする生き方も、間違いはないといえそうです。
薬師寺のお坊さんからの伝言?をひとこと。
最近薬師寺に来る人が少なくて、雨の季節など、誰も来ない日もあるとか……そんな時「伽藍」は「ガラン」としています。
どうぞ皆様お参りに来てください……だそうです。